1. はじめに
2018年頃から日本で爆発的な人気を誇ったタピオカドリンク。しかし、2021年以降、その勢いは急激に衰え、多くのタピオカ専門店が閉店を余儀なくされました。一時は街中に数多くのタピオカ店が並び、長蛇の列ができるほどの人気を誇っていたものの、現在ではその数は大幅に減少しています。
この急激なブームの終焉には、市場の飽和・消費者の嗜好変化・経済的要因 など、さまざまな理由が関係しています。本記事では、タピオカブームがなぜ生まれ、なぜ急速に衰退したのかを詳細に分析し、飲食業界が今後どのように変化していくのかを考察します。
2. タピオカブームの背景

2.1 なぜタピオカが流行したのか
タピオカブームは、以下のような要因が組み合わさって誕生しました。
- SNSの影響(インスタ映え)
- タピオカドリンクはカラフルで写真映えしやすく、InstagramやTwitterなどのSNSで拡散されやすかった。
- 「映える」飲み物として、若者を中心に話題に。
- アジア圏での人気
- 台湾をはじめとするアジア各国でタピオカミルクティーが定番ドリンクとなり、日本へもトレンドが波及。
- フランチャイズモデルの拡大
- 多くの企業がタピオカビジネスに参入し、フランチャイズ展開によって店舗数が急増。
- 高単価ビジネスとしての成功
- 1杯500~700円の価格設定で高い利益率を確保できるビジネスモデル。
これらの要素が重なり合い、一大ブームを巻き起こしました。
2.2 タピオカ屋の急増と市場の過熱
タピオカドリンクが人気を博したことで、多くの企業や個人事業主がタピオカビジネスに参入しました。結果として、日本全国でタピオカ専門店が急増し、一部のエリアでは過剰な競争が生まれる事態となりました。
- 2018年〜2020年の急成長
- 飲食チェーンだけでなく、個人経営のタピオカ店も多くオープン。
- 主要都市だけでなく、地方都市にもタピオカブームが波及。
- 市場の供給過多
- 競争が激化し、価格競争に突入。
- 飽和状態により、一部店舗は採算が取れなくなる。
3. タピオカ屋が減った理由
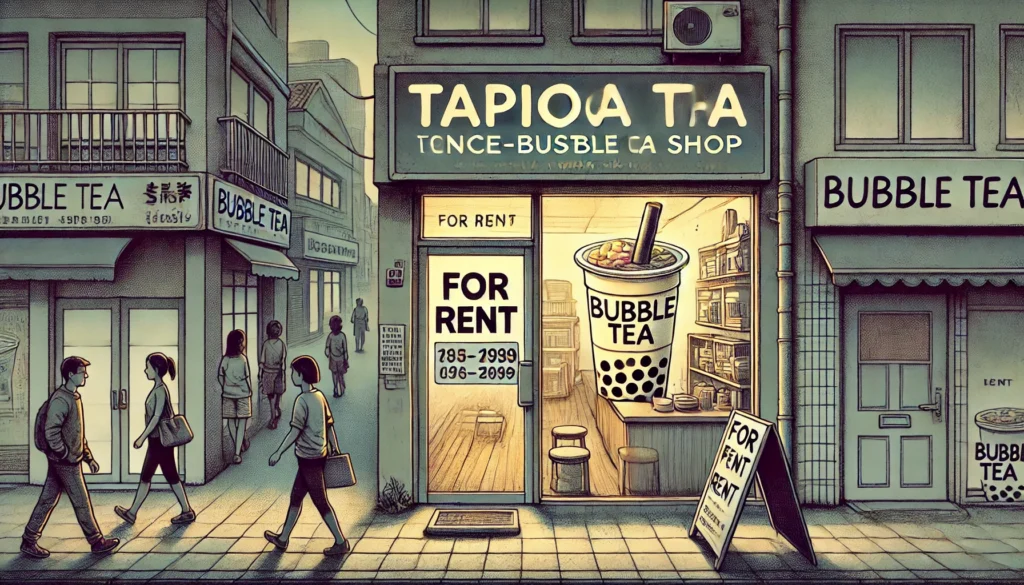
3.1 市場の飽和と競争の激化
タピオカ専門店が乱立したことで、競争が激化。特に価格競争が進んだ結果、収益性が低下し、多くの店舗が撤退を余儀なくされました。
- 似たような店舗が増え、差別化が困難に。
- 価格競争の結果、利益率が低下。
3.2 消費者トレンドの変化
- 「インスタ映え」ブームの終焉
- SNS映えを重視した飲食ブームの移り変わり。
- 次のトレンド(チーズティー、韓国スイーツなど)に消費者の関心が移行。
- 健康志向の高まり
- タピオカは高カロリー・高糖質であることが知られるようになり、健康志向の消費者に敬遠されるようになった。
3.3 新型コロナウイルスの影響
- 外出自粛により客足が減少
- テイクアウト需要の減少
- タピオカは時間が経つと品質が落ちるため、デリバリーに向いていなかった。
3.4 経営コストの上昇
- 原材料費の高騰
- タピオカの輸入コストが増加し、利益が圧迫された。
- 人件費・賃料の上昇
- 都市部では高額な家賃が大きな負担となった。
3.5 リピーター不足
- 一度試せば満足する消費者が多く、定番メニューとして定着しなかった。
- タピオカの「特別感」が薄れたことで、リピーターの獲得が難しくなった。
4. タピオカブームの終焉が示す教訓
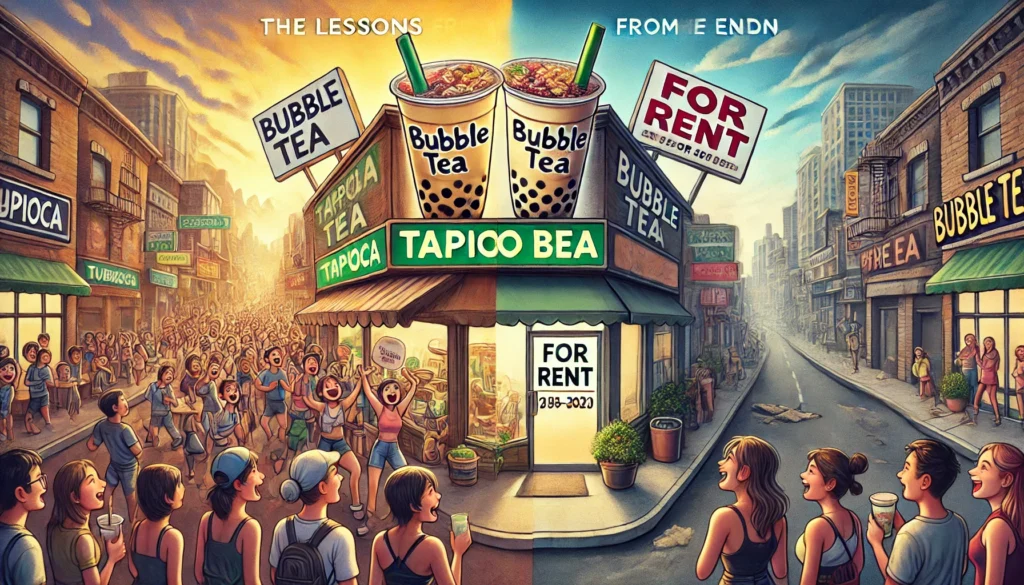
4.1 一過性のブームに依存するリスク
- 持続可能なビジネスモデルの必要性
- ナタデココやパンケーキと同様、一時的な流行に依存すると持続が難しい。
4.2 差別化の必要性
- 価格競争に巻き込まれないために、ブランドの独自性を確立することが重要。
- メニューの多様化、ターゲット層の拡大が鍵となる。
4.3 フランチャイズ展開の課題
- 急成長モデルの落とし穴
- 加盟店が増えすぎると、品質管理や利益分配の問題が発生する。
5. タピオカ業界の今後の展望

5.1 生き残るタピオカ屋の戦略
- 健康志向のメニュー開発
- 低糖タピオカやオーガニック素材の活用。
- フードメニューとの融合
- スイーツや軽食との組み合わせ。
5.2 次に来る飲食トレンド
- 台湾スイーツ(豆花、仙草ゼリー)
- 高級ドリンク路線(プレミアム抹茶、黒糖)
- ノンアルコールカクテル市場の成長
6. まとめ
タピオカ屋の急激な増加と衰退は、飲食業界における一過性のブームのリスクを如実に示しています。市場の飽和、消費者の嗜好変化、経営コストの増加などが影響し、現在では多くのタピオカ店が撤退を余儀なくされました。
今後の飲食業界では、トレンドのみに頼らず、持続可能なビジネスモデルを構築することが求められるでしょう。
7. Q&A セクション
Q1. タピオカ屋はなぜ急激に増えたのですか?
A:
タピオカブームの背景には、SNS(特にInstagram)での拡散力の強さがありました。見た目が可愛く「インスタ映え」することが若者を中心に人気を集めた大きな要因です。また、台湾発の飲料として話題性が高く、日本でも急速に人気が拡大しました。さらに、一杯500〜700円という高単価な価格設定が可能だったため、フランチャイズ展開が急速に進み、多くの事業者が参入したことも店舗の急増につながりました。
Q2. なぜタピオカ屋は閉店が相次いでいるのですか?
A:
主な理由は 市場の飽和・消費者の嗜好変化・経営コストの増加 にあります。タピオカ専門店が急増したことで供給が需要を上回り、競争が激化しました。また、「インスタ映え」ブームの終焉や、健康志向の高まりによって消費者の関心が薄れたことも大きな要因です。加えて、新型コロナウイルスの影響で外出を控える人が増え、売上が低迷したことが店舗閉鎖につながりました。
Q3. タピオカのカロリーや糖質はどれくらいですか?
A:
タピオカミルクティー1杯(約500ml)には 300〜500kcal 程度のカロリーが含まれており、糖質も 50〜80g 程度と高めです。特に黒糖タピオカミルクティーなどは糖分が多く、健康志向の消費者から敬遠される傾向があります。
Q4. タピオカに代わる次の飲食ブームは何ですか?
A:
最近注目されているのは、以下のような飲食トレンドです。
- 台湾スイーツ(豆花・仙草ゼリー)
- チーズティー
- プロテインドリンク
- ノンアルコールカクテル
特に健康志向の高まりにより、低糖・低カロリーのドリンク への関心が高まっています。
Q5. タピオカ屋は今後生き残ることができるのでしょうか?
A:
生き残るためには、健康志向のタピオカドリンク や 新メニューとの融合 など、差別化戦略が必要です。例えば、低糖タピオカやオーガニック素材を使用した健康志向のメニュー、スイーツとのセット販売などが考えられます。また、タピオカだけに依存せず、複数のメニューを展開することでリスクを分散することも重要です。
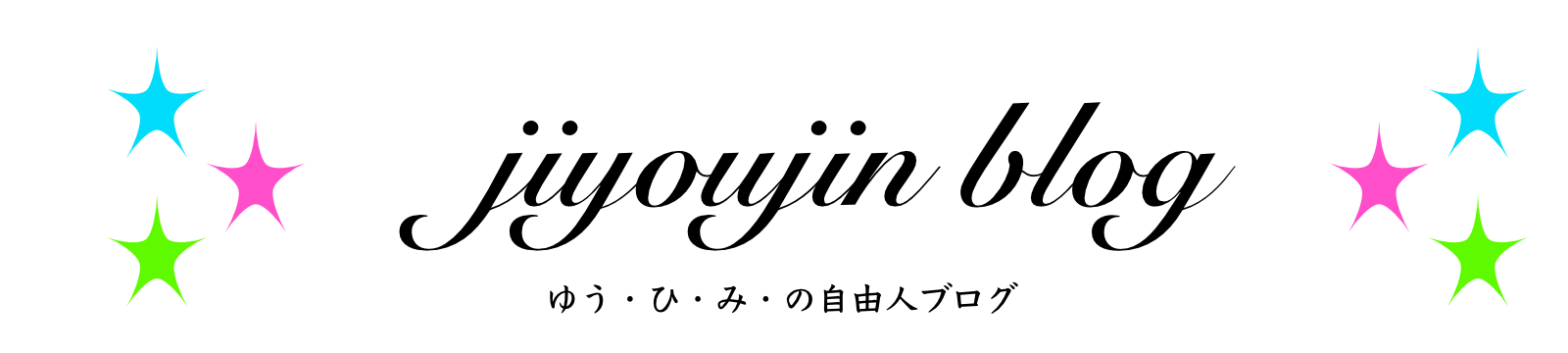
コメント